
2024年3月26日に、ジュリア・ブライアン=ウィルソン『アートワーカーズ――制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践』がフィルムアート社より刊行された。労働やジェンダーの問題を扱う本書は、日本のアート・ワーカーにとって示唆に富む内容になっている。ここでは、本書の簡単な概要と、出版を記念して行われたイベントの内容をレポートする。
多声的な翻訳の試み

『アートワーカーズ』書影(装丁デザイン:熊谷篤史)
ジュリア・ブライアン=ウィルソン『アートワーカーズ――制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践』( https://www.filmart.co.jp/books/9-784-8459-2308-3/)が、2024年3月26日にフィルムアート社より刊行された。『アートワーカーズ』は、ジュリア・ブライアン=ウィルソン氏が2009年に出版した著作Art Workers: Radical Practice in the Vietnam War Eraの邦訳である。竹内均氏が運営するART RESEARCH ONLINE(https://www.artresearchonline.com/home)上で2021年12月から始まった『アートワーカーズ』読書会を皮切りに、アートワーカーズ翻訳プロジェクト実行委員会(高橋沙也葉/長谷川新/松本理沙/武澤里映)が実に二年以上の歳月をかけて本書を翻訳した[1]。
[1] その間、著者のブライアン=ウィルソン氏や竹内氏はもちろんのこと、解題執筆者の笹島秀晃氏、沢山遼氏、鵜尾佳奈氏、井上絵美子氏、浜崎史菜氏、勝俣涼氏、注釈の翻訳を担当してくださった森田理美氏、久光真央氏、橋爪大輔氏、大磯日向子氏、森下響氏、イベントに登壇してくださった吉澤弥生氏、池上裕子氏、菅野優香氏、通訳の樅山智子氏、山田カイル氏、イベントをともに主催してくださった京都芸術センターのみなさま、清水知子氏をはじめとする東京藝術大学のみなさま、フィルムアート社の臼田桃子氏、白尾芽氏、ブックデザインを担当してくださった熊谷篤史氏、ポスターデザインを担当してくださった大槻智央氏など、本当に多くの方々にご協力いただいた。熱意をもって本書の出版に関わってくださったみなさまに、改めて感謝を申し上げたい。
『アートワーカーズ』は、1960年代アメリカで、自らを芸術労働者(アートワーカー)と定義することでアクションを起こしたアーティスト・批評家たちの作品や活動を徹底的に掘り下げたケーススタディによって構成されている。扱われたのは、ミニマルな作品によって「水平化」を目論んだカール・アンドレ、ブルーカラー労働者との同一化を夢想したロバート・モリス、批評や小説の執筆、キュレーションという「労働」を通してフェミニズムに接近したルーシー・リパード、そして情報を提示する作品によって制度批判を行ったハンス・ハーケである。本書を邦訳するにあたって、著者によって新たに書き下ろされた日本語版の序文と、各章に専門家による解題が付け加えられた。
2024年3月、著者でコロンビア大学美術史・考古学部教授のブライアン=ウィルソン氏を日本に招き、3月14日に京都芸術センター、3月17日に東京藝術大学で、それぞれ出版記念イベントを実施した。この出版イベントは、『アートワーカーズ』が提起する労働やジェンダーをめぐる問題について、日本のオーディエンスによりアクチュアルなものとして受け取ってもらいたいという思いから企画されたものである。イベントへの来場が叶わなかった多くの方々に向けて、以下ではイベントでなされた議論の一端を紹介したい(ただし、本レポートはイベントの文字起こしではないことを断っておく)。
開催日時:2024年3月14日(木)18:30〜20:30
会場:京都芸術センター 大広間
登壇者:ジュリア・ブライアン=ウィルソン(コロンビア大学)、吉澤弥生(共立女子大学)、アートワーカーズ翻訳プロジェクト実行委員会

「芸術労働者(アートワーカー)はいかに社会と関わりうるか?」イベント風景(撮影:高橋沙也葉)

イベント会場には茶菓子と関連書籍を並べた(撮影:高橋沙也葉)
京都では、「芸術労働者(アートワーカー)はいかに社会と関わりうるか?」と題し、文化政策や芸術にまつわる労働環境の専門家である吉澤弥生氏をお招きした。長らく芸術と労働の問題に取り組んでこられた吉澤氏にご登壇いただくことで、『アートワーカーズ』を日本における芸術と労働の問題、そして来場者が抱える不安や問題と接続させるようなイベントを目指した。なごやかな雰囲気の中で参加者が意見交換できるよう、京都芸術センターの大広間(座敷!)を会場とし、来場者にはお茶やお菓子を楽しみながらイベントに参加していただいた。限られた時間ではあったが、実際に様々な職種の方々から今抱えている問題についての質問が挙がり、実りあるディスカッションが展開されたのではないかと思う。

登壇者のジュリア・ブライアン=ウィルソン氏(撮影:高橋沙也葉)
それではイベントの内容に入っていこう。はじめにブライアン=ウィルソン氏から、本書の内容を紹介するプレゼンテーションが行われた。ブライアン=ウィルソン氏は、本書はアートワーカーズ連合、アーティストによる「アートワーカー」や労働者への同一化、そしてベトナム戦争に関するアーティストの活動などをめぐる、様々な矛盾を問うために執筆されたと話す。
それはいかなるものか。例えばアートワーカーズ連合に関わっていたアーティストたちは、デモやビラの作成を行い、美術館による戦争、人種差別、性差別への加担を批判する政治活動を展開した。しかし一方で、本書が扱うアンドレ、モリス、リパード、ハーケの芸術活動は、政治的主張とは全く関係しないかのような抽象性を持つものでもあった。このように、本書が扱う作家たちの個人の政治活動と、作品の形式が持つ政治性の双方について考えてみたかったとブライアン=ウィルソン氏は語る。
他に、アーティストたちが行った政治活動自体にも矛盾がある。例えば当時、アーティストたちはストライキを行ったが、本来ストライキとは雇用主に対する争議行為であり、どこにも雇われていないアーティストはその矛先を向ける仮想敵を設定する必要があった。そのためアーティストたちは美術館を雇用主の代理として捉えて戦おうとしたが、それでは矛盾を乗り越えることができなかったとブライアン=ウィルソン氏は指摘する。
こうした矛盾への問いに応答するため、『アートワーカーズ』では、アンドレ、モリス、リパード、ハーケのケーススタディが続く。なかでも本イベントでは、モリスとアンドレの内容が重点的に紹介された。
英語版『アートワーカーズ』のカバーイメージにも使用されている、ホイットニー美術館の個展で行われた、労働を可視化するモリスのパフォーマンスは、本書で詳細に論じられている。この個展において、モリスは設営作業自体をパフォーマンス化し、自らもその作業に参加することで労働者階級と同一化しようと試みた。しかし、そこにもやはり様々な矛盾が存在した。なかでも重要であったのは、1960年代の労働者階級は、ナショナリズム、反コミュニズム、人種差別などの思想から、戦争支持の立場をとっていたという点である。そのような労働者階級の立場は、奇しくもモリスの個展と同時期に起こったヘルメット暴動[2]によってあからさまに表出した。モリスがホイットニー美術館で労働のパフォーマンスを行っていたちょうどそのときにこのヘルメット暴動が起きたことで、もはやモリスと労働者の連帯は不可能になり、この個展を閉幕させるというアートストライキが生まれていく。モリスと労働者の間には階級の問題が明らかに存在しており、モリスはそれを解消することができなかったのである。
[2] 1970年5月8日に、戦争支持派の建設労働者数百人が反戦運動を行う学生を暴行した事件。
続いて、本書におけるアンドレの作品の分析についても紹介された。アンドレは労働者の象徴であるツナギを着用し、反戦運動に参加した人物である一方で、彼が制作する作品は非常にミニマルで抽象的なものだった点が特徴的である。例えば、《マグネシウム-亜鉛の平地》(1969)は、平面的であり、作品の上を歩くことができるために、アンドレ自身は政治的なメッセージを持った作品であると認識していた。しかしこの作品は非常に抽象的であり、彼が共闘しようとした労働者にそのメッセージが伝わるわけではない。ゲリラ・アート・アクション・グループ《近代美術館からのロックフェラー家全員の即時退陣を求める声明》(1969)など、同時期の非常に直接的な政治性を持ったパフォーマンスと比較すると、アンドレの作品の非ポピュリズム的な性格がより明確になるだろう。
さらにこの《マグネシウム-亜鉛の平地》の素材に関して、ブライアン=ウィルソン氏は非常に重要な指摘を行っている。ブライアン=ウィルソン氏はボルチモア美術館でこの作品を調査するなかで、作品の一部であるプレートを裏返してみたのだという。その結果、ベトナムを焼き尽くしたナパーム弾を製造していたダウ・ケミカル社の製品を用いていたことが、裏面の刻印から明らかになった。アンドレは反戦を訴えながら、まさに戦争に加担していた企業の製品を作品に使用するという矛盾した行動をとっていたのである。
以上、モリスとアンドレについての簡単な報告からでも、彼らの労働者との同一化への憧憬とその不協和音の一端が垣間見えただろう。労働者をはじめとする社会的弱者との連帯は、今日のアートワールドにおいても広く見られる現象である。しばしばその連帯のインパクトにスポットライトが当たりがちだが、そこに存在するであろう欲望や危うさにも注意を払う必要があることに、改めて気づかせるプレゼンテーションであった。

登壇者の吉澤弥生氏(撮影:高橋沙也葉)
ブライアン=ウィルソン氏のプレゼンテーションを受けて、登壇者である吉澤氏からは会場に議論を開くため、芸術と労働やフェミニズムに関する興味深いデータと取り組み事例の一部が紹介された。最初に示されたのは美術業界のジェンダーギャップ (出典: 表現の現場調査団「表現の現場ジェンダーバランス白書」2022)である。このデータによると、東京6美術大学における学生の男女比が約3:7であるのに対し、教授となると約4:1と男女比が逆転する。吉澤氏が語ったように、このような深刻なジェンダーギャップが美術業界における女性のロールモデルの不在や、ハラスメントの温床になっていることは疑う余地もない。その他にも、文化予算の国際比較(出典:文化庁「諸外国の文化予算に関する調査 報告書」2016)、労働に関するジェンダーギャップ(出典:独法労働経済研究・研修機構「早わかり グラフでみる⻑期労働統計」2023、内閣府「男女共同参画白書」2023)、労働組合の現状(出典:厚生労働省「令和4年労働争議統計調査の概況」2023)といったデータ、及びアーティスツ・ギルド Artistsʼ Guilds(https://artists-guild.net/)やアーティスツ・ユニオン Artistsʼ Union (http://artistsunion.jp/index.html)などの取り組み事例が紹介され、日本とアメリカが共通して抱える構造的な問題が可視化された。
その後、質疑応答の時間が取られた。中でも特に印象的であったのは、アートの労働現場に蔓延るやりがい搾取についての議論である。ブライアン=ウィルソン氏によると、アメリカでもやりがい搾取と似た意味を持つ「心理的な報酬(psychic reward)」という語があり、特に看護や教育、アート、NGO団体などのジェンダー化された職種において、好きなことをしているからという理由で賃金を低く設定する風潮があるという。
こうした空気感が蔓延する中で、自らを「アートワーカー」と自称することは、労働者としての自覚や権利を再認識するために有効であるとブライアン=ウィルソン氏や吉澤氏は語る。本イベントで議論されたように、まずは私たち自身が「労働者」なのだと認識し、雇用主がいる場合は労働組合などを通して自らの権利を主張する、あるいは労働条件を明示し、契約書を作成するなど、できることから取り組んでいく必要があるだろう。

日本のアート業界の労働環境について興味深い議論が展開された(撮影:高橋沙也葉)
開催日時:2024年3月17日(日)14:00~17:00
会場:東京藝術大学上野キャンパス・ 音楽学部5号館 5-109
講師:ジュリア・ブライアン=ウィルソン(コロンビア大学)
討議者:池上裕子(神戸大学、現在は大阪大学)、菅野優香(同志社大学)
司会:清水知子(東京藝術大学)

「 “アートワーカー”はどこにいる?——60年代アメリカの芸術、労働、ジェンダー」イベント風景(撮影:黑田菜月)

背面からわずかにこぼれる蛍光色の発光が美しいポスター(デザイン:大槻智央、撮影:黑田菜月)
東京では、「 “アートワーカー”はどこにいる?——60年代アメリカの芸術、労働、ジェンダー」と題し、池上氏と菅野氏に討議者としてご登壇いただいた。池上氏は2009年に出版された『アートワーカーズ』原著と同時期にラウシェンバーグに関する著作[3]を発表し、ブライアン=ウィルソン氏と同じくアメリカ美術史における重要な転換期に立ち会い、社会的美術史(social art history)の潮流の中で仕事をしてきた戦後アメリカ美術の専門家である。
[3] Hiroko Ikegami, The Great Migrator: Robert Rauschenberg and the Global Rise of American Art, MIT Press, 2010.
菅野氏はセックスワーク等の女性の労働と表現の関係についても探求してきたクィア/フェミニスト映画理論・批評の専門家であり、ブライアン=ウィルソン氏とはクィア・スタディーズやフェミニズムという観点で研究上の共通点を持つ。それぞれ異なる点でブライアン=ウィルソン氏と文脈を共有しているお二人をお招きすることで、東京では1960年代アメリカの芸術、労働、ジェンダーについての専門的なイベントとなることを目指した。
タイトルの「“アートワーカー”はどこにいる?」は、後ほど詳述するアナ・メンディエタの死に関与したと考えられるアンドレの作品を収蔵することや、回顧展を開催することに対する抗議活動にて使用されているフレーズ、「アナ・メンディエタはどこにいる?」(“Where Is Ana Mendieta?”)になぞらえたものである。この抗議活動は家庭内暴力や、女性、ノンバイナリー、トランスジェンダー、人種の問題に対する美術館の責任をも問い直すものだ。本イベントもまたこうした抗議活動に共鳴し、問題意識を共有したものとなることを願い、このタイトルを掲げた。
本イベントにおいても、はじめにブライアン=ウィルソン氏から本書の内容を紹介するレクチャーが行われた。中でも本レポートでは、時間の都合上京都のイベントでは十分に言及されなかったリパード、ハーケについての紹介を記録しておく。
リパードはアートワーカーズ連合で活動し、その後フェミニスト運動も展開した人物である。彼女は黒人の大工や看護師の女性とフェミニズムの運動を通して展覧会を組織するなどの活動を行い、本書が扱う他のアーティストが失敗した労働者との連帯を実現したとブライアン=ウィルソン氏は評価する。リパードは、女性の評価されてこなかった仕事、家庭の中での仕事、子供を巡る権利に関して、階級や人種を越えて連帯することができた人物だったのである。
しかし興味深いことに、労働者階級と連帯するリパードはそれ以前に、アンドレの作品のようなミニマルで抽象的な芸術が反戦運動に有効であると考え、その美学自体が平和的なものであると信じていた。
それが、アルゼンチンへの訪問によって変化することとなる。政治的なアクションを起こすアルゼンチンのアーティストたちとの出会いを通して、彼女は男性アーティストが中心であったミニマルな芸術から、女性アーティストによるクラフト的な芸術へと関心を移すようになった。
リパードがこのように立場を変化させた理由の一つに、アートワーカーズ連合自体に性差別が存在したことが挙げられるだろう。実際、アートワーカーズ連合の活動の中で、家政婦や秘書のように扱われることに辟易とした女性たちは、よりフェミニスト的な活動を行う団体に移っていった。リパードが言うように、男性アーティストが着々と有名になっていく中で、女性たちはフェミニストとして政治化されていったのである。
またハーケは、1974年に《ソロモン・R・グッゲンハイム美術館理事会》という作品を制作し、理事たちの所属企業もまた軍事衝突と関わっていることを明らかにした。しかしこの作品が発表される以前、すでにアートワーカーズ連合が理事たちについて調査し、その結果を展示することで美術館への抗議を示すという試みを行っている。ハーケが明らかにアートワーカーズ連合のアクティヴィズムの手法から影響を受けていたという点もまた、ブライアン=ウィルソン氏が本書で明らかにした重要な研究成果の一つである。
さらに、ブライアン=ウィルソン氏のレクチャーでは2024年3月11日に国立西洋美術館で行われた抗議活動についても話題が及んだ。この抗議活動は、3月12日に開幕した展覧会「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?──国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」の記者向け内覧で、参加作家がイスラエルのパレスチナ侵攻ならびに同館スポンサーの川崎重工に対する抗議を表明したものである。奇しくも、『アートワーカーズ』で取り上げられた1970年のアートストライキと共鳴するようなプロテストが行われたことも本イベントでは共有され、議論の対象となった。

国立西洋美術館で行われた抗議活動に言及するブライアン=ウィルソン氏(撮影:黑田菜月)


登壇者の池上裕子氏(上)、菅野優香氏(下)(撮影:黑田菜月)
その後、池上裕子氏と菅野優香氏によるブライアン=ウィルソン氏のレクチャーへの応答が行われた。まず池上氏による質問を受けてブライアン=ウィルソン氏は扱われた作家たちの本書への反応を紹介した。次に、菅野氏は国立西洋美術館での抗議について触れ、抗議を表明した作家たちを称えると同時に、メディアがこの抗議について、女性作家が中心的な役割を占めたという点に過度に注目しているように思われるという、抗議活動とジェンダー(表象)の問題にも注意を促した。

活発な質疑応答が行われた(撮影:黑田菜月)
その後は翻訳チームからのコメントと、質疑応答が続いた。質疑応答において印象的であったのは、マチズモ(男性優位主義)というトピックについての議論である。池上氏からはこのマチズモに関連して、アートワーカーズ連合と同時代の日本の事例である美共闘が紹介された。美共闘もまた制度批判を行った団体であるが、特異なのは、美共闘の制度批判はアーティスト自身の内に向かう点であるという。その結果美共闘のメンバーは、自らに内在する制度性を批判するために一年間芸術制作を止めるという決断に至る。池上氏は、この現実には維持できない実践に向かう論理展開こそがマチズモと関わると指摘する。美共闘の数少ない女性アーティストである石内都が語ったように、過度にロジックを重視するこの試みは明らかに「男の闘争」だったからだ。
石内はその後、「集団エス・イー・エックス」という女性のグループを結成したが、それはすぐに破綻した。彼女は当時、ウーマン・リブの運動にも違和感を抱き、男性と生活していたという[4]。今日的な視点からみると、フェミニストが男性と生活することにはなんの矛盾もない。しかし、当時は家父長制があまりに強力であったがゆえに、女性たちの連帯が阻害された現実があったのだと池上氏は指摘する。
[4] 石内都オーラルヒストリー、小勝禮子と中嶋泉によるインタヴュー、2010年12月20日、日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ(oralarthistory.org)
菅野氏もまた、「アートワーカーズ」というアイデンティティや協働に内在するマチズモについて言及した。菅野氏は、アートワーカーズというコレクティブなアイデンティティや、今日尊ばれている協働、リーダーシップにはマチズモの問題が関係しており、さらに『アートワーカーズ』が扱う事例の場合、そこに人種や階級の問題も含まれていると指摘する。菅野氏が語ったように、アートワーカーズ連合がうまくいかなかった理由の一つに、マチズモの問題が挙げられるという見方もできるだろう。
最後に、本イベントを通して言及されたメンディエタの死について触れておきたい。キューバ人アーティストのメンディエタは、1985年に夫アンドレとともに暮らしていた34階の部屋から転落死した。アンドレは殺人容疑で起訴されたが、1988年に行われた裁判では証拠不十分で有罪とはならなかった。しかし、アンドレが殺人裁判では異例のベンチ・トライアル(陪審員制度を用いない裁判)を要求したことや、メンディエタが転落する直前に「ノー、ノー、ノー」という叫び声を聞いたというドアマンの証言[5]、アンドレの一貫性のない言い訳、メンディエタが転落した際の詳しい状況については語られなかったことなどから、この判決には今なお多くの人が疑いのまなざしを向けている[6]。この事件は、アンドレについて語る際に決して等閑視することのできないものである。
[5] Alex Greenberger, “The Death of Ana Mendieta, Explained: Why Carl Andre Faced a Murder Trial, and How He Was Acquitted,” ARTnews, January 25, 2024, https://www.artnews.com/art-news/news/ana-mendieta-death-explained-carl-andre-murder-trial-acquittal-1234694056/
[6] Jan Hoffman, “Rear Window: The Mystery of the Carl Andre Case,” the Village Voice, August 7, 2020 (Originally published March 29, 1988), https://www.villagevoice.com/rear-window-the-mystery-of-the-carl-andre-case/
ブライアン=ウィルソン氏は、もし現在もう一度この本を書き直すなら、決してアンドレに一章を割くことはしなかっただろうと繰り返し語る。すでに名声を得、殺人の疑いがかけられたアンドレではなく、メンディエタのような、これまで十分に語られてこなかった多くの人種的、ジェンダー的、性的マイノリティの作家についての仕事をすることを彼女は望むからだ。私たちひとりひとりが生涯にできる仕事量はそれほど多くない。限られた時間のなかで、誰の声を拾い上げるために自らの時間を使うのか。私たちもまた、何について調査し、何について語るのか、何に自らの時間や紙幅を割くのかという問題と無関係ではない。仕事を巡るトピック、時間、そしてその成果が持つ政治性に、私たちもまた自覚的である必要があるだろう。
最後に司会の清水氏は、原著が世界金融危機の最中に刊行されたことに触れ、労働者という存在が資本主義システムに対してどういう問いを持つのかについて改めて考え直す時期の著作だったのではないかと指摘した。また本書は、誰もが生産的であれ、誰もが創造的であれとされるポスト・フォーディズム時代における労働者のあり方や、1960年代と同様に戦争の時代を生きる私たちの生活・労働には不可視化された暴力的構造が基盤にあること、そして一人のアーティストの背後に多くの労働者や関係性が存在することを問い直す、重要な意義を持つと清水氏は語る。私たち一人一人が、それぞれの文脈からそのような複雑な力学に目を向け、ケアを基盤とする生活・労働環境を構築する必要があるとし、本イベントを締めくくった。
以上二つの出版イベントについて、簡単ではあるがその内容をレポートしてきた。本書の内容を起点とし、各登壇者によって労働やジェンダーをめぐる今日的な問題への接続がなされたことで、実りあるイベントになったと感じている。
同時に、二つのイベントが提起した美術業界のジェンダーギャップ、アートワーカーとしての自認、抗議活動における女性への過度な注目、マチズモの問題、メンディエタの死、そして語ること、書くことをめぐる責任といったトピックは、art for allが継続して取り組んできた活動とも重なり合うものである。これらのトピックについて様々な角度から考え続ける磁場を形成するためにも、『アートワーカーズ』への関心をきっかけとしてart for allに出会う、あるいはart for allをきっかけに『アートワーカーズ』を読むといった循環が生み出されることを期待したい。このレポートをきっかけに、多くの方が本書を手に取ってくださることを願っている。
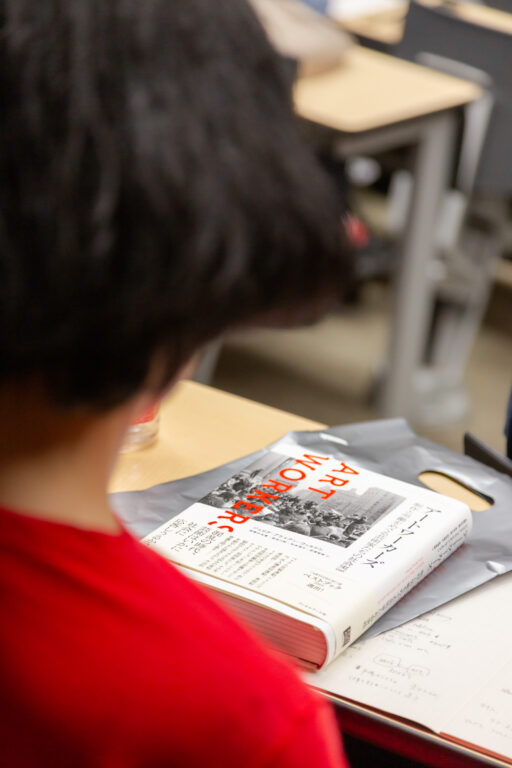
多くの方に本書が届くことを願って(撮影:黑田菜月)
松本理沙
京都芸術大学 専任講師
まつもと・りさ 京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。京都芸術大学通信教育部芸術学部専任講師。専門は美術史、表象文化論。特にアメリカや日本におけるパブリック・アート、ソーシャリー・エンゲージド・アートなどについての研究を行う。共訳書に『アートワーカーズ──制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践』(フィルムアート社、2024年)。